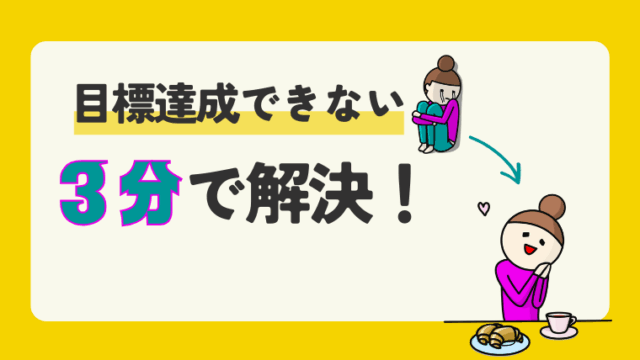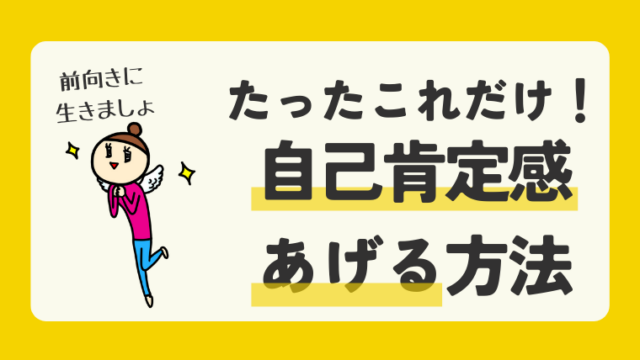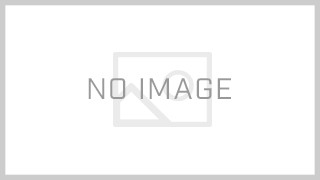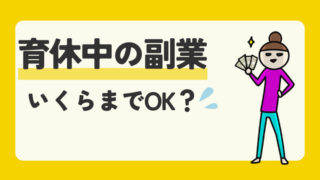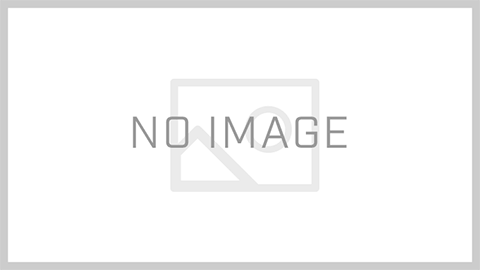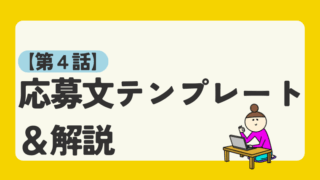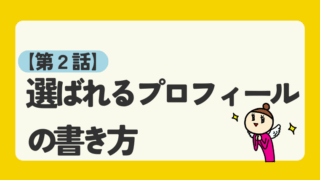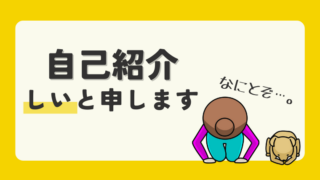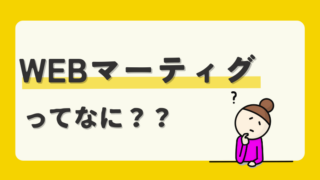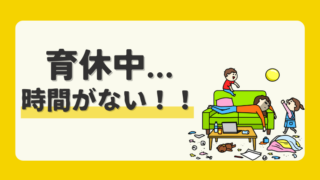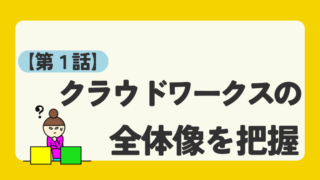「いつも完璧を目指して、結局、疲れてしまう…」
「人に頼れない。だって中途半端な結果にはしたくないから」
そんなふうに、完璧主義で生きづらさを感じていませんか?
かつての私もそうでした。
何をしても満足できず、自己否定のループにハマる日々。
でもある日気づいたんです。
完璧主義って「性格」じゃなくて「思考のクセ」だった、と。
クセなら変えられる——
この記事では、心を軽くする「完璧主義の治し方」をお伝えします。
- まずは自分を知ることから|完璧主義セルフチェックリストと落とし穴
- 【完璧主義の治し方①】「まずやってみる」思考で完璧スイッチをオフにしよう
- 【完璧主義の治し方②】心のブレーキを外す「80点で合格」という新ルール
- 【完璧主義の治し方③】小さな成功(スモールウィン)の積み重ねで行動できない自分を卒業!
- 【完璧主義の治し方④】視野を広げて全体像を掴む!目的思考のすすめ
- 【完璧主義の治し方⑤】「全部やらなきゃ」を手放す!優先順位のシンプルな決め方
- 【完璧主義の治し方⑥】もう一人の自分を持つ!客観視トレーニングで内なる鬼上司をリセット
- 【完璧主義の治し方⑦】失敗は成長のタネ!「ミスしても大丈夫」マインドセット
- 7つの習慣で「完璧主義の呪い」を解き放つ!今日から始める一歩
まずは自分を知ることから|完璧主義セルフチェックリストと落とし穴

完璧主義とは、「常に最高の結果を出さなければならない」「失敗は許されない」という、まるで心の中にいる厳しい上司のような思考パターンです。それは、丁寧さや几帳面さとは少し違います。
あなたは完璧主義?セルフチェックリスト
これ、3つ以上当てはまったら要注意。
自分を追い詰める“完璧スイッチ”が入っているサインかもしれません。
✔︎ 何かを始める前に、「本当にうまくできるかな…」と不安になる。
✔︎ 失敗すると、「もう終わりだ…」と極端に落ち込んでしまう。
✔︎ 「もっと準備しなきゃ」が口癖で、なかなか行動に移せない。
✔︎ 少しでもミスをすると、「やっぱり自分はダメだ…」と感じてしまう。
✔︎ 周りの人の評価が気になって、なかなか自分の意見を言えない。
✔︎ 「もっと頑張らないと」と、常に自分を追い立ててしまう。
✔︎ 自分の成果に満足できず、「まだまだ…」といつも不満を感じている。
✔︎ 時間やエネルギーを、まるで無限にあるかのように使ってしまう。
もし当てはまる項目が多くても、どうか自分を責めないでくださいね🌟
これは、あなたが真剣に物事に取り組む証拠でもあるのです。ただ、その真面目さが、あなたを少し苦しめているのかもしれません。
その行動、本当に必要?完璧主義がもたらす意外な弊害
「ちゃんとしなきゃ」「完璧じゃないとダメ」って思いが、気づかないうちに一日中つきまとってくる。朝起きたときも、寝る前も、なんだかずっと気が休まらない。
そしてこの完璧主義、実は落とし穴があるんです。頑張っているつもりが、逆に自分を追い込んでしまったり、なかなか前に進めなくなったり…。思い当たること、ありませんか?
ここまで読んで「全部当てはまる…」と感じた方もいるかもしれません。
でも大丈夫。あなたが真剣に頑張ってきた証です。 この先の習慣から、少しずつ肩の力を抜くヒントをお届けします。
【完璧主義の治し方①】「まずやってみる」思考で完璧スイッチをオフにしよう

璧主義の人って、「最初の一歩」がやたら重く感じませんか?
頭では動いたほうがいいって分かってる。でも、足が前に出ない。私もよくそのループにハマってました。
この悪循環を断ち切るために、「まず動く、そして考える」という習慣を身につけましょう。
「5分だけ」ルールの活用
何かを始めるのに躊躇しているときは、「とりあえず5分だけやってみる」と自分に言い聞かせてみましょう。
たとえば:
- レポート作成に取りかかるのが億劫なら、「5分だけ目次を書いてみる」
- 部屋の片付けが大変そうなら、「5分だけ一箇所を整理する」
- 英会話の練習が不安なら、「5分だけ音読してみる」
多くの場合、いったん始めてしまえば、そのまま続けられることが多いものです。
私は提出書類に取り掛かるのが苦手なので、5分だけとりあえず概要を読むようにしています。最初の「行動のハードル」を極力下げたことで、後回しにしすぎることがなくなりました!
「完璧な計画」より「不完全な行動」を
かつて私は、仕事のプロジェクトにおいて、完璧なプランを練ってから上司に報告をしようと1週間を費やし、いざ上司に報告したら「まだプラン練ってたの!?」と言われた苦い経験があります…。「完璧な計画を立ててから行動しよう」と思っていると、いつまでたっても行動できません。なぜなら、「完璧な計画」などというものは存在しないからです。
70%の準備で行動を始め
20%は行動しながら学び
残りの10%は柔軟に調整する
というアプローチの方が、結果的に「完璧」に近づけるのです。
世界的起業家のリチャード・ブランソンも「準備が整ってから始めるのではなく、始めながら準備を整えよ」と言っています。
「完璧を目指すより、まず80点で行動する」。
それが、心にゆとりを持つための第一歩です。
「時間の壁」テクニック
「考えすぎて動けない」という方には、タイマーを活用した「時間制限法」がおすすめです!制限時間を設けることで、脳は「完璧」より「完了」を優先するよう切り替わります。私はブログの執筆で行き詰まったとき、メンターから教わった「25分集中法」(ポモドーロ・テクニック)をよく使います。「25分だけ集中して、何が書けるか」と時間を区切ったことで、「できるところまでやってみよう!」と取り掛かれるようになりました。
例えば:
- 「この企画書は30分で書く」と決める
- 「この絵は2時間で仕上げる」と時間枠を設定する
- 「3時間以内に部屋の片付けを終わらせる」と決める
時間制限を設けることで、完璧を求めすぎる余裕がなくなり、必然的に「まずやってみる」姿勢が身につきます。
【完璧主義の治し方②】心のブレーキを外す「80点で合格」という新ルール

完璧主義者の多くは、自分に対して「100点以上」の基準を課しています。しかし、この高すぎる基準が行動の妨げになり、ストレスの原因となっています。
「80点主義」とは、「80点で合格、それ以上は加点」と考える思考法です。
「80点でOK」と思えるだけで、心がすっと軽くなるんです。
「足りない部分はあとで直せばいい」——そう思えると、動き出しやすくなります。
なぜ80点で十分なのか
現実世界では、「100点の完璧」を求めることで得られるメリットより、「80点を早く出す」ことで得られるメリットの方が大きいことがほとんどです。
「早く80点を出す」ことで得られる3つの効果
1. フィードバックの宝庫
80点の状態で人に見せることで、思いもよらなかった視点や改善点が見えてくる
2. 成長の加速
多くの「80点の経験」を積む方が、少ない「100点の経験」より成長が速い
3. 脳のリソース節約
80点で「完了」とすることで、次の挑戦へのエネルギーが残る
以前の私は、ブログ記事を「100点」に仕上げようと何週間も修正を重ね、結局月に1本も投稿できないこともありました。でも「80点でOK」と思えるようになってからは、週1本ペースで公開できるように。更新頻度が上がったことで、検索からの流入も増え、読者とのやり取りも増えていきました。
あなたの「80点」はどこ?場面別の具体例
「80点でいい」と言われても、具体的にどう判断すればいいのか悩む方もいるでしょう。以下に、様々な場面での「80点」の目安を紹介します。
仕事の資料作成の場合:
- 100点:文章の一言一句まで推敲し、デザインも細部までこだわり、何度も何度も確認する
- 80点:内容が正確で、主要な情報が網羅されており、読みやすい構成になっている
新しい趣味(絵画など)の場合:
- 100点:プロ並みの技術で、細部まで完璧に描き込む
- 80点:基本的な形が捉えられており、自分が表現したかったものが伝わる
家事(料理など)の場合:
- 100点:レストランのような見栄えと味、完璧な段取り
- 80点:栄養バランスが取れており、家族が美味しく食べられる
あなた自身に「許可を出す」3つの魔法の言葉
完璧主義者が「80点主義」を実践するには、意識的に「自分への許可」を出す練習が必要です。
私が最も効果を感じた「自分への許可」の言葉を紹介します:
1. 「今日の私は、これで十分😊」
作業を始める前に、具体的な「80点ゴール」を決める
例:「今日のプレゼン資料は、骨子と主要なデータが入っていれば十分」
2. 「これは成長過程の一部🌱」
特に新しいことに挑戦するときは、「練習」と位置づける
例:「これは10回目の料理挑戦。毎回少しずつ上達していけばいい」
3. 「フィードバックが成長のカギ🗝️」
早めに形にして、周囲の反応を取り入れる価値を認識する
例:「80点の状態で上司に見せることで、自分では気づかなかった視点が得られる」
これらの「許可の言葉」を、スマホの壁紙にしたり、デスクに貼ったりして、日常的に目にする工夫も効果的です。私はタスクに「80点で完了できたか?」という項目を入れて、毎日意識的にチェックするようにしています!
【完璧主義の治し方③】小さな成功(スモールウィン)の積み重ねで行動できない自分を卒業!

友達が「ケーキ失敗しちゃった…やっぱり私、向いてない」と落ち込んでいたら、きっと「初めてなんだから当たり前だよ」って励ましますよね。でも、自分に対してはどうでしょう?「私には才能がないんだ」なんて言っていませんか?
実はその裏にいるのが、あなたの中の“内なる批評家”。この声に振り回されないコツが、「小さな成功体験=スモールウィン」の積み重ねなんです。
自分を応援する“新しい習慣”をつくろう
自分を責める代わりに、「小さな一歩」を喜ぶ癖をつけること。それがスモールウィンです。
自分の中に“応援団長”を住まわせるイメージで、日々の行動を肯定してあげましょう。
具体例:「自分応援ルール」日常にこう取り入れる!
🏠 家事での応援団長の声
・「全部掃除しなくても、本棚だけできたらそれで勝ち」
・「食器洗ってないけど、そのぶん早く寝られてラッキー!」
💼 仕事での応援団長の声
・「この企画書、まずは80%で提出してフィードバックを活かそう」
・「To Doが全部終わらなくても、3つやれたら拍手!」
📚 自己成長での応援団長の声
・「5分だけでも続けられた。継続してる自分すごい」
・「1ページしか読めなくても、0ページよりずっといい!」
習慣は“思考の癖”から生まれる
私自身、以前は「寝る前にキッチンを片づけないと落ち着かない」タイプでした。
子どもと寝落ちした翌朝、キッチンが荒れた状態だと、自分を責めてしまっていたんです。
今はこう思うようになりました。
「1日くらい食器洗わなくたって死なないし、むしろぐっすり眠れてラッキー♪」
そう思えるようになったのは、「小さなOK」を自分に出す訓練をしてきたから。
完璧じゃなくても、「できたこと」に目を向けてあげること。
それが、あなたの行動力を少しずつ取り戻してくれるはずです。
完璧じゃなくても、少しずつ進んでる。
自分の中にいる批評家を、今日から応援団長に変えてみませんか?
【完璧主義の治し方④】視野を広げて全体像を掴む!目的思考のすすめ

完璧主義の人は、とにかく“細部”まで手を抜けません。
プレゼン資料を作るときも、
✔️ 説明の構成
✔️ 色やフォントの統一
✔️ 図解の配置
✔️ 表紙のデザイン…
どれも「ちゃんとしなきゃ」と思ってしまう。
でも、その結果どうなるかというと──
時間が足りない。
疲弊する。
そして、提出ギリギリにあわてて仕上げる。
私もまさにこれでした。
目的から逆算する「★評価」で、こだわるポイントを見極める
そんな私を変えたのは、ある先輩の一言。
「“目的に沿ってこだわる場所を決める”のが、賢い仕事の仕方だよ」
そこで私は、自分なりのルールを作ってみました。
その名も、「★3つルール」!
💡例:クライアント向けプレゼン資料の場合
-
★3つ(=最重要)
→「相手が理解しやすい構成」
└ ここには1番時間をかける! -
★2つ(=必要だけどやりすぎない)
→「内容に合った図解やグラフ」
└ 読みやすさの補助にとどめる -
★1つ(=時間をかけすぎない)
→「フォントや色の統一、装飾」
└ サッと整えるだけで十分!
以前、ある資料づくりで、表紙のデザインと装飾にやたら時間をかけてしまったんです。
結果、肝心の中身(構成)が浅くて、先方に
「で、結論は何ですか?」とズバッと聞かれてしまったことがありました…涙
そのとき気づきました。
“全部完璧”にしようとすることが、逆に目的から遠ざけていたんだと。
「優先力」は目的から生まれる
大切なのは、“全部ちゃんと”ではなく、“目的にちゃんと沿うこと”。
こだわりたい気持ちは大事。でも、そのパワーを「どこに注ぐか」で、結果は大きく変わります。
完璧主義を否定しなくていい。
むしろそれは、強みでもあります。
でもその強みを発揮するには、「選ぶ力」=目的思考が必要。
全部やらなくていい。
本当に大事なところに、★3つをつけてあげてくださいね🌟
【完璧主義の治し方⑤】「全部やらなきゃ」を手放す!優先順位のシンプルな決め方
 「全部やりたい」「全部ちゃんとやりたい」
「全部やりたい」「全部ちゃんとやりたい」
それが完璧主義の人にとって一番の悩みですよね。
私も、タスクリストを見るたびに思ってました。
「これも大事、あれも今すぐやらなきゃ…!」
でも結局、どれも中途半端で疲弊して終わる日々。
あるセミナー講師の言葉にハッとしたことがあります。
「“重要だけど急がないこと”をこなせる人が、長く成果を出す」
聞いた瞬間、「確かに…!」と腹落ち。
“急ぎじゃないから”と後回しにしていた本当に大切なこと、ありませんか?
アイゼンハワーマトリクスで、タスクを4つに分けてみよう
これは、タスクを「緊急」「重要」の2軸で分類する方法です。
-
①重要×緊急:すぐやる(例:今日の打ち合わせ準備)
-
②重要×緊急じゃない:計画的にやる(例:資格の勉強、健康管理)
-
③緊急×重要じゃない:できれば手放す(例:急ぎの電話対応)
-
④重要じゃない×緊急じゃない:やらない(例:なんとなくのネットサーフィン)
この「②」を日常でどれだけ優先できるかが、実は未来を大きく変える鍵なんです。
「仕事も育児も趣味も全て充実させるタスク管理術4STEP」はこちら
私が試してみたToDoリストの工夫
私の場合、リストのタスクが全部「やらねば」で埋まっていました。
なので、今はこうしています👇
✔️ リストの横に「今日これだけやれればOK!」の赤丸をつける!
これを始めてから、タスクが「敵」から「味方」に変わった感覚があるんです。
達成できた日は「やった!」という実感がちゃんとあって、
できなかった日も「大事なことはやれた」と思えるから、罪悪感が減りました。
【完璧主義の治し方⑥】もう一人の自分を持つ!客観視トレーニングで内なる鬼上司をリセット
完璧主義の正体は、自分だけに異常に高い基準を課す「鬼上司」。そんな“鬼上司の声”に振り回されそうなときこそ、
「冷静な第三者としての自分」を登場させるようにしてるんです。
完璧主義に対抗するのは「冷静な審査員の目」
イメージは、感情に左右されない冷静な審査員。
根拠や目的を軸に、ムダなく成果を判断するタイプの存在です。
この「もう一人の自分」を登場させることで、思考が驚くほど整理されます。
あくまで自分の中にいる“味方”だから、ジャッジされるストレスもありません。
今すぐできる!3ステップの客観視トレーニング
【STEP1】思考を書き出す(モヤモヤの可視化)
まずは、どこまでやるべきか分からなくなった原因を全部書き出してみてください。
感情が絡んでいるほど、言語化するだけで視界がスッとクリアになります。
【STEP2】“判断基準”をあてはめてみる
「これは成果に直結する?」「誰にとって価値がある?」
そんな視点でフィルターをかけていくと、意外と不要なこだわりが炙り出されてきます。
私はよく、「これは3日後の自分も気にする?」と自問しています。
この一言だけで、優先順位がかなり整理されるんです。
【STEP3】「親友にどうアドバイスするか?」を考える
最後にもう一段やさしい視点を。
「親友が同じことで悩んでいたら、自分はどう声をかけるか?」と想像してみてください。
これ、2014年のハーバード大学の研究でも実証されていて、
“自分事”より“他人事”の方が冷静に判断できるという心理効果があるそうです。
「冷静な自分」を呼び戻すことで、思考が整う
悩みや不安に飲み込まれそうなときこそ、
「これは本当に重要?」「3日後の私も納得する?」と、“冷静な自分”から問いを投げてみましょう。
すると…
✔️ 判断がブレなくなる
✔️ 優先順位がつけやすくなる
✔️ 「これでいい」と納得して手放せる
など、完璧主義の根っこをほどいていく力になってくれます。
完璧主義が暴走するとき、私たちは“厳しすぎる上司”のように自分を追い詰めがち。
でも本当に必要なのは、冷静に状況を判断してくれる、もう一人の自分の目なんです。
「どこまでやるべき?と迷ったら、“審査員モード”に切り替える」
このクセがつくだけで、ぐっと身軽に行動できるようになりますよ。
【完璧主義の治し方⑦】失敗は成長のタネ!「ミスしても大丈夫」マインドセット
 「失敗したら終わり」と思っていませんか?私もそうでした。「完璧な記事が書けた!」と満足していたら、納品報告を忘れていたせいで「納期遅れ」と思われてしまったことがあります。作業内容じゃなく“報告”で信頼を落とすなんて…と大反省。今ではToDoに「報告」も必ず入れています。
「失敗したら終わり」と思っていませんか?私もそうでした。「完璧な記事が書けた!」と満足していたら、納品報告を忘れていたせいで「納期遅れ」と思われてしまったことがあります。作業内容じゃなく“報告”で信頼を落とすなんて…と大反省。今ではToDoに「報告」も必ず入れています。
完璧主義な人ほど失敗を恐れますが、実は失敗こそが“自分の伸びしろ”を教えてくれるヒント。そのための3つの視点があります。
①「これはどんな学びだった?」と問い直す
→ 冷静になって、失敗の本質を見つめると成長ポイントが見える。
②「未来の自分ならどう活かす?」と考える
→ つまずきも、他人への共感や再発防止に変えられる。
③「今すぐできる、誠実なリカバリを選ぶ」
→ 完璧な挽回じゃなくても、“できることをすぐやる”姿勢が信頼をつくります。
「失敗=終わり」ではなく、「失敗=始まり」。うまくいかなかった経験が、自分を鍛え、やがて挑戦する力に変わっていきます。完璧じゃない自分を、少しずつ肯定していきましょう。
7つの習慣で「完璧主義の呪い」を解き放つ!今日から始める一歩
 完璧主義との闘いは、一日で終わるものではありません。でも、この7つの習慣を少しずつ取り入れることで、あなたの人生は確実に軽やかになっていきます。
完璧主義との闘いは、一日で終わるものではありません。でも、この7つの習慣を少しずつ取り入れることで、あなたの人生は確実に軽やかになっていきます。
完璧主義を手放す7つの習慣おさらい:
- 「まず動く、そして考える」 – 5分だけのルールで行動のハードルを下げ
- 「80点で合格」と基準を下げる – 完璧より「十分に良い」を目指す
- 小さな成功体験を積み重ねる – 大きな目標を小さなステップに分解
- 「木も森も見る」目的思考 – こだわるべきポイントを見極める
- 「全部やらなきゃ」を手放す – 優先順位をつけ、重要なことに集中
- 「もう一人の自分」で客観視 – 内なる厳しい声に振り回されない
- 「失敗は学びのタネ」と捉える – 挑戦する勇気を取り戻す
これらは「完璧主義をゼロにする」ためではなく、「完璧主義と上手に付き合う」ための習慣。どれか一つでも、今日から始められるものはありませんか?
私も完璧主義との付き合いは日々の戦い。でも、この習慣を一つひとつ取り入れるうちに、不思議と肩の力が抜け、むしろ以前より良い結果が出せるようになりました。失敗を恐れずに挑戦できるようになり、人生の景色が変わってきたんです。
今日は、この中から「一番しっくりくる習慣」をひとつだけ選んで、小さく始めてみませんか?「5分だけノートに書く」「友達に一度だけ意見を聞いてみる」…そんな小さな一歩でOK。
完璧な「完璧主義克服」なんて目指さなくていい。少しずつ、自分のペースで、あなたらしい「ちょうどいい生き方」を見つけていきましょう。
あなたの中にある「もっと自由に、もっと自分らしく生きたい」という小さな声。その声に、今日、耳を傾けてみてください。
行動を始めるためのステップ🐾
これらの習慣を身につけるために、まずは以下のステップから始めてみましょう。
✔︎ この記事の中で、最も共感できた習慣を1つ選ぶ
✔︎ その習慣を実践するための「小さな一歩」を具体的に決める
✔︎ カレンダーや日記で実践を記録し、継続する
✔︎ 少しずつ他の習慣も取り入れていく
最後までお読みいただきありがとうございました。